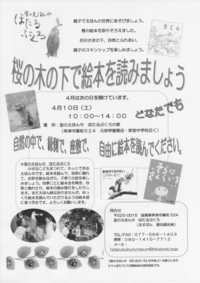2009年11月22日
「食の安全・安心を考える意見交換会2009」に行ってきました

県の生活衛生課・食の安全推進室が、「食の安全・安心を考える意見交換会2009」を開催するというので、昨日行ってきました。
生産者、加工業者、流通業者、消費者、行政などいろいろな立場の人が100人ほど参加し、テーブルに5人ずつに分かれて座って、意見交換をしました。
話し合いの最初のお題は「2039年、滋賀県の食はどのようになっているでしょうか?」。
私は消費者として夢や希望を語りたいなと思ったのですが、現場の生産者の方々は非常に厳しい認識で、このままいったら第一次産業はすべて崩壊する、日本の食を支える人はいなくなる、農地が荒れることで水も守られなくなり、琵琶湖は汚れ災害は増える、と悲観的な意見が次から次へと……。また、食品製造業者の方の中には、栄養はいくらでも化学合成できるので、これからはサプリメント食で十分というような意見を言われる方もいました。
なんで「食」がそんな悲しいことになっちゃったのかなとみんなで考えていくと、親から子へと食文化が継承されていないことや、食料の生産現場が暮らしの場から離れて見えなくなったこと、本当においしいものを食べていないこと、食への感謝が薄れていることなどの意見が出てきました。
「サプリメントでは栄養は摂れても心は育たない」
「おいしいものを食べている人は食に対する感謝があるけれど、そうでないひとは食べることに関心がない」
「自然回帰が必要。グローバルからローカルへ」
などの言葉が心に残りました。
食べることは生きること。
それがないがしろにされている社会は、すさんだ社会になるのは当然だろうと思えます。
あまのじゃくくらぶでも、今年は親子クッキング体験やおせち料理づくりの企画を通して、食の問題に取り組んでいます。私たちらしく、肩肘張らずにじっくりと。
30年後、どんな社会を創りたいのか、子どもたちにどんな社会を残してやりたいのか、それをきちんと考え実行していくことは、私たち大人の責任です。
一緒に考えていってくださるとうれしく思います。
(げんげん)
Posted by 遊人里(ゆとり) at 23:59│Comments(0)
│ゆとりなひとびと
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。